教師を育て、音楽授業を創造する場 Japan Association for the Study of School Music Education Practice
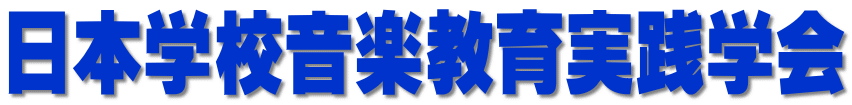
研究大会
研究奨励賞
第1回(2006) 受賞論文
| 題目 | 戦後日本の「音楽づくり」にみられる学力観-「構成的音楽表現」からの問い直し- | |
| 著者 | 小島律子(大阪教育大学) | |
| 選考理由 | 「音楽づくり」について、学力の観点から問い直すことによって、新しく我が国の学校教育に導入されたこの教材を、子どもの人間形成に寄与する重要なものとして究明し、その学習方法を原理的に示したことが教育実践学の学術論文として評価された。 | |
| 審査委員会 | 審査委員長 | 石田一志(音楽評論家、くらしき作陽大学教授) |
| 審査委員 | 西村 朗(作曲家、東京音楽大学教授) | |
| 松本絵美子(東京都青梅市立教育委員会指導主事) | ||
| 西園芳信(鳴門教育大学教授) | ||
| 神原陸男(洗足学園大学短期大学教授) | ||
| 加藤博之(昭和音楽大学助教授) | ||
第2回(2007) 受賞論文
| 題目 | 音楽表現活動の相互交流の場にみる子どもの意味生成の様相 | |
| 著者 | 斉藤百合子(大阪教育大学附属平野小学校) | |
| 選考理由 | 音楽授業における相互交流の意味を質の認識としての意味生成にあることを究明し、指導者が相互交流の場面で持つべき新たな視点を提出したことが教育実践学の学術論文として評価された。 | |
| 審査委員会 | 審査委員長 | 石田一志(音楽評論家、くらしき作陽大学教授) |
| 審査委員 | 西村 朗(作曲家、東京音楽大学教授) | |
| 藤沢章彦(国立音楽大学教授) | ||
| 西園芳信(鳴門教育大学教授) | ||
| 神原陸男(洗足学園大学短期大学教授) | ||
| 松本絵美子(東京都文京区本郷小学校校長) | ||
第3回(2008) 受賞論文
| 題目 | 音楽鑑賞における批評の教育的意義とそのアセスメント―高等学校芸術音楽の授業実践と発話の解釈を通して― | |
| 著者 | 宮下俊也(奈良教育大学)・岩田真理(大阪府立福井高校) | |
| 選考理由 | 高等学校の音楽鑑賞について、批評行為を構造化し、その構造を論理化することで音楽鑑賞における批評の方法論を導出している。この方法論は、高校生を対象とした鑑賞指導の新しい境地を開拓するもので、教育実践学の学術論文として評価される。 | |
| 審査委員会 | 審査委員長 | 石田一志(音楽評論家、くらしき作陽大学教授) |
| 審査委員 | 西園芳信(鳴門教育大学教授) | |
| 神原陸男(洗足学園大学大学教授) | ||
| 松本絵美子(東京都文京区本郷小学校校長) | ||
| 以下理事以外(外部委員) | ||
| 西村朗(作曲家、東京音楽大学) | ||
| 石田一志(音楽評論家、倉敷作陽大学教授) | ||
| 藤澤章彦(国立音楽大学教授) | ||
第4回(2009) 受賞論文: 該当者なし
第5回(2010) 受賞論文
| 題目 | 文化的側面を扱うことによる音楽的な教育効果-小学校2年生のトガトンの実践的分析を通して- | |
| 著者 | 小川由美(大阪教育大学附属平野小学校) | |
| 選考理由 | 学習指導要領の指導内容に示されていない小学校での文化的側面の扱いについて、実践事例をもって論じた点に独創性が認められる。また、単に文化的側面の理解を学習指導することのみならず、そのことと形式的側面、及び内容的側面とを関連付けて実践を展開し知見を提出したことは、小学校における文化的側面の学習指導の在り方として新しい実践を示唆し、今後の学校の音楽教育への新しい道筋を拓くものとなっている。 | |
| 審査委員会 (◯印は審査委員長) |
理事以外(外部委員) | 西村 朗(作曲家、東京音楽大学教授) |
| 石田一志(音楽評論家、くらしき作陽大学教授) | ||
| ◯ 西園芳信(鳴門教育大学教授) | ||
| 常任理事 | 宮下俊也(奈良教育大学准教授) | |
| 松本絵美子(東京文京区立本郷小学校校長) | ||
| 中島卓郎(信州大学教育学部教授) | ||
第6回(2011) 受賞論文
| 題目 | 構成的音楽表現におけるイメージの分節化を促すための指導の一考察 | |
| 著者 | 渡辺尚子(神戸市立西山小学校) | |
| 選考理由 | 本論文は、子どもの音楽表現活動におけるイメージについて、「分節化」の観点から明らかにし、その研究成果から子どもの思考力を育成する際の教師の手立てを示唆したものである。本研究は、子どもの思考力育成の点から今後の学校音楽教育への新しい道筋を拓くものである。以上の点から本論文は、教育実践学研究の論文として評価される。 | |
| 題目 | 「中学校におけるわらべうた遊びの教材化の可能性 -『構成的音楽表現』を原理とする授業構成-」 |
|
| 著者 | 横山真理(関市立富野中学校) | |
| 選考理由 | 本論文は、子どもの音楽表現活動におけるイメージについて、「分節化」の観点から明らかにし、その研究成果から子どもの思考力を育成する際の教師の手立てを示唆したものである。本研究は、子どもの思考力育成の点から今後の学校音楽教育への新しい道筋を拓くものである。以上の点から本論文は、教育実践学研究の論文として評価される。 | |
| 審査委員会 (◯印は審査委員長) |
理事以外(外部委員) | 西村 朗(作曲家、東京音楽大学教授) |
| 石田一志(音楽評論家、くらしき作陽大学教授) | ||
| ◯ 西園芳信(鳴門教育大学教授) | ||
| 常任理事 | 宮下俊也(奈良教育大学准教授) | |
| 松本絵美子(東京文京区立本郷小学校校長) | ||
| 中島卓郎(信州大学教育学部教授) |
第7回(2012) 受賞論文
| 題目 | 芸術的探究としての音楽創作授業における子どもの問題解決過程に関する教育実践学的研究 -デューイの探究理論を手がかりに- | |
| 著者 | 兼平佳枝(北海道教育大学附属札幌中学校) | |
| 選考理由 | 本論文は、芸術的探究としての音楽創作授業における子どもの問題解決過程に関する教育実践学的研究である。文献より芸術的探究の理論的枠組みを導き、その枠組みを基に音楽創造授業を構想・実践・分析するというように、論述展開の筋が一貫している。先行研究のレビューも行き届いており、何よりも子どもの芸術的探究としての問題解決過程の姿を具体的に把握しているところは、授業内容としてもユニークであり、また実践の的確な分析を含めて臨場感の高いものとしてまとめられている。このような点から、本論文は、教育実践学の研究として評価される。 | |
| 審査委員会 (◯印は審査委員長) |
理事以外(外部委員) | 西村 朗(作曲家、東京音楽大学教授) |
| 石田一志(音楽評論家、くらしき作陽大学教授) | ||
| ◯ 西園芳信(鳴門教育大学教授) | ||
| 常任理事 | 宮下俊也(奈良教育大学教授) | |
| 松本絵美子(東京文京区立本郷小学校校長) | ||
| 山下敦史(札幌市立南が丘中学校教諭) | ||
第8回(2013) 受賞論文
| 題目 | 異文化芸術を経験することの意義について―音楽学習における文化的側面の提示と生徒の受容から― | |
| 著者 | 金奎道(兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科博士課程) | |
| 選考理由 |
本論文は、異文化芸術を経験することの意義と方法の理論的根拠をJ.デユーイの芸術論に求め、その上で異文化芸術の学習は、音楽の文化的側面を関連させ学習することが有効であるという仮設を立て、実践・検証している。具体的には、韓国の民俗芸能「カンカンソーレ」を教材とし、この教材で音楽の形式的側面、内容的側面、技能的側面と関連させながら音楽の文化的側面をパフォーマンス・視覚手段・言語による説明によって学習する授業を構成し、実践している。そして、生徒の行為や言語による記述という事実に基づいて文化的側面についての理解の様相を明らかにし、仮設に対応する結論を導き出している。 異文化芸術を学習することを通して、異文化に対する理解を深めると共に、自国の文化を理解し、尊重する態度を育てていくことは、現在音楽科に求められている大きな課題の一つであり、本論文はその解決に資する内容である。このような点から本論文は、教育実践学の研究として評価される。 |
|
| 審査委員会 (◯印は審査委員長) |
理事以外(外部委員) | 西村 朗(作曲家、東京音楽大学教授) |
| 石田一志(音楽評論家、くらしき作陽大学教授) | ||
| ◯ 西園芳信(鳴門教育大学 理事・副学長教授) | ||
| 常任理事 | 清村百合子(京都教育大学准教授) | |
| 尾崎祐司(上越教育大学講師) | ||
| 山下敦史(札幌市立南が丘中学校教諭) | ||
第9回(2014) 受賞論文:該当者なし
第10回(2015) 受賞論文
| 題目 | 「表情カード」を利用した内部世界の表出支援-発達障害のある児童への音楽学習過程― | |
| 著者 | 尾崎祐司(上越教育大学) | |
| 選考理由 |
本論文は、発達障害のため内部世界の表出に困難な児童生徒の認知への支援として、鑑賞の授業で「表情カード」(「温和」や「緊張」など人間の顔の表情をイラストに表したもの)を用い、その有効性を明らかにしたものである。 |
|
| 題目 | 「単元『百人一首をつくってうたおう』にみる話す言葉からうたへの変容過程に関する一考察」 | |
| 著者 | 山本祐子(東海学院大学) | |
| 選考理由 |
本論文は、単元「百人一首をつくってうたおう」という小学校6年生を対象にした実践研究を通して、話すことばからうたへの変容過程を明らかにしたものである。その変容過程は、次のようになる。 話す言葉は、最初に拍節が現れ、次に抑揚がつき、母音がのびる。さらに速度の緩急、声の音色や強弱の変化という要素が働き、うたへと変容していく。そして、このような音楽の諸要素の出現は、内面のイメージの形成・発展と連動しながら多様になっていくと結論づけている。 本論文は、ことばと歌との関係についてうたうという行為からの生成過程に着目した実践的方法が評価される。 |
|
| 審査委員会 (◯印は審査委員長) |
理事以外(外部委員) | 西村 朗(作曲家、東京音楽大学教授) |
| 石田一志(音楽評論家、くらしき作陽大学教授) | ||
| ◯西園芳信(鳴門教育大学 理事・副学長教授) | ||
| 常任理事 | 清村百合子(京都教育大学准教授) | |
| 山下敦史(札幌市教育委員会指導主事) | ||
| 清水 匠(茨城大学教育学部附属小学校教諭) |
第11回(2016) 受賞論文
| 題目 | 音楽科授業における集団思考成立の条件 ―小学校1年生の「図形楽譜づくり」の場合― | |
| 著者 | 小林佐知子 | |
| 選考理由 |
本論文は、小学校1年生の音楽科授業において、特に『図形楽譜づくり』を通して集団的思考成立の条件を実践的に検証し明らかにしたものである。 | |
| 審査委員会 (◯印は審査委員長) |
理事以外(外部委員) | 西村 朗(作曲家、東京音楽大学教授) |
| 石田一志(音楽評論家、くらしき作陽大学教授) | ||
| ◯ 西園芳信(鳴門教育大学名誉教授、聖徳大学兼任講師) | ||
| 常任理事 | 清村百合子(京都教育大学准教授) | |
| 清水 匠(茨城大学教育学部附属小学校教諭) | ||
| 田中龍三(大阪教育大学教授) |
第12回(2017) 受賞論文:該当者なし
第13回(2018) 受賞論文
| 題目 | 音楽鑑賞学習での批評文にみる身体表現の機能-共同行為における動きと言語の関係に着目して- | |
| 著者 | 鉄口真理子(鳴門教育大学) | |
| 選考理由 |
本論文は、音楽鑑賞学習において、身体表現を共同行為と捉え、共同行為における動きと言語との関係に着目し、批評文における身体表現の機能を実践的に検討し明らかにしたものである。 | |
| 審査委員会 (◯印は審査委員長) |
理事以外(外部委員) | 西村 朗(作曲家、東京音楽大学教授) |
| 石田一志(音楽評論家) | ||
| ◯ 西園芳信(鳴門教育大学名誉教授、聖徳大学兼任講師) | ||
| 常任理事 | 清村百合子(京都教育大学教授) | |
| 清水 匠(茨城大学教育学部附属小学校教諭) | ||
| 田中龍三(大阪教育大学特任教授) |
第14回(2019) 受賞論文
| 題目 | 音楽づくりにおける子どもの目論見形成にみるイマジネーションの働き | |
| 著者 | 岡寺 瞳 | |
| 選考理由 |
本論文は、音楽づくりにおいて子どもが目論見を形成していく過程にイマジネーションがどのように働くか、実践研究を通して明らかにしたものである。 | |
| 審査委員会 (◯印は審査委員長) |
理事以外(外部委員) | 西村 朗(作曲家、東京音楽大学教授) |
| 石田一志(音楽評論家) | ||
| ◯ 西園芳信(鳴門教育大学名誉教授、聖徳大学兼任講師) | ||
| 常任理事 | 清村百合子(京都教育大学教授) | |
| 兼平佳枝(大阪教育大学准教授) | ||
| 山﨑浩隆(熊本大学准教授) |
第15回(2020) 受賞論文
| 題目 | 問題解決としての音楽的思考におけるリフレクションの機能-思考の連続性に着目して- | |
| 著者 | 藤本佳子 | |
| 選考理由 |
本論文は、問題解決としての音楽的思考におけるリフレクションの機能について、実践研究を通して明らかにしたものである。 | |
| 審査委員会 (◯印は審査委員長) |
理事以外(外部委員) | 石田一志(音楽評論家) |
| 西村 朗 (作曲家、東京音楽大学教授) | ||
| 〇 西園芳信 (鳴門教育大学名誉教授、聖徳大学特命教授) | ||
| 常任理事 | 清村百合子(京都教育大学教授) | |
| 兼平佳枝(大阪教育大学准教授) | ||
| 山﨑浩隆(熊本大学准教授) |
第16回(2021) 受賞論文
| 題目 | 器楽授業での「表現」への展開過程における身体活動の機能―「素材」から「媒体」への変容に着目して― | |
| 著者 | 渡邊真一郎 | |
| 選考理由 |
本論文は、器楽授業での「表現」への展開過程における身体活動の機能について、素材から 媒体への変容に着目して究明したものである。 | |
| 審査委員会 (◯印は審査委員長) |
理事以外(外部委員) | 石田一志(音楽評論家) |
| 西村 朗 (作曲家、東京音楽大学教授) | ||
| 〇 西園芳信 (鳴門教育大学名誉教授、聖徳大学特命教授) | ||
| 常任理事(内部委員) | 清村百合子(京都教育大学教授) | |
| 兼平佳枝(大阪教育大学准教授) | ||
| 山﨑浩隆(熊本大学教授) |
第17回(2022) 受賞論文:該当者なし
第18回(2023) 受賞論文
| 題目 | 音楽科・体育科・「運動会」のクロスカリキュラム実践における身体表現の発展にみる教科等内容の作用 | |
| 著者 | 石光 政德 | |
| 選考 理由 |
本論文は、音楽科・体育科・「運動会」のクロスカリキュラム実践において、子どもの身体表現の発展過程に各教科等内容がどのように作用したかを教育実践学の観点から明らかにしたものである。 結論は次のとおりである。音楽科では、楽曲を知覚・感受したことが、表現のイメージの形成に作用した。体育科では、表現したいイメージを基に身体の動きの工夫が行われた。「運動会」では、観客という他者意識を持つことで、協力して見栄えの良い作品にしようと欲求が生まれ、音楽の諸要素を意識したダイナミックな身体表現を創作することに作用した。 つまり、表現を軸とした音楽科・体育科・「運動会」のクロスカリキュラムによって、教科等内容が相互に関連をもって身体表現を発展させるのに作用し、三者の教科等内容が統合された身体表現が生まれた。 本論文は、次のような点から評価される。第1は、問題が多いとされる運動会の身体表現の創作のために、音楽科と体育科と「運動会」の教科等内容を関連付けたクロスカリキュラムにおいて、デューイの芸術的経験における「表現」の概念から教科等横断の相互作用・相乗効果を図ったことである。第2は、現在学校教育で開発・実践が求められ、教育現場で模索がなされている「教科等横断型授業」について、実践としてモデルを提案したことである。 | |
| 審査委員会 (◯印は審査委員長) |
理事以外(外部委員) | 石田一志(音楽評論家) |
| 西村 朗(作曲家、東京音楽大学教授) | ||
| 〇 西園芳信 (鳴門教育大学名誉教授、聖徳大学兼任講師) | ||
| 常任理事(内部委員) | 小川由美(琉球大学教育学部教授) | |
| 鉄口真理子(鳴門教育大学教授) | ||
| 清水 匠(土浦市立第五中学校主幹教諭) |
第19回(2024) 受賞論文
| 題目 | 中学校音楽科授業での創作表現における生徒による素材の選択行為の機能 | |
| 著者 | 大和 賛 | |
| 選考 理由 |
本論文は、中学校音楽創作授業において、生徒が内的世界と外的世界を相互作用させながら音楽創作していく過程を、表現の素材の選択行為という観点から分析し、表現における素材の選択行為の機能を明らかにしたものである。 結論は次のとおりである。一つは、音楽創作過程において、素材の選択行為は、創作を遂行する際にイメージや記憶等の内的素材を基に、それを実現するために外的素材であるリズムや音の重なり等の選択肢から適切なものを選び問題を解決する際の手段になる。二つは、音楽創作過程において、素材の選択行為によって、外的素材を選択する過程で生徒の内的素材が引き出され、このことで創作表現において外的素材と内的素材を相互に関連させることになる。本論文は、教育実践学の論文として次の点から評価される。第1に、デューイ芸術論において芸術表現成立の理論となる内的素材と外的素材の相互作用という問題を、素材選択を視点に中学校の創作授業を対象に実践的に究明したことである。第2に、表現活動の授業において、生徒が表現の素材選択行為に注目することで、生徒自身が内的世界に注目し表現の主体として活動していくことができることを明らかにしたことである。 | |
| 審査委員会 (◯印は審査委員長) |
理事以外(外部委員) | 石田一志(音楽評論家) |
| 松尾葉子(指揮者) | ||
| 〇 西園芳信 (鳴門教育大学名誉教授、聖徳大学兼任講師) | ||
| 常任理事(内部委員) | 小川由美(琉球大学教育学部教授) | |
| 鉄口真理子(鳴門教育大学教授) | ||
| 清水 匠(土浦市立第五中学校主幹教諭) |
第20回(2025) 受賞論文
| 題目 | 保育者・初等教員養成における遊び直し経験を軸とする『わらべうた』の授業構成―『子どもの学びの相似形』としての音楽授業の展開のために― | |
| 著者 | 宮澤多英子 | |
| 選考 理由 |
本論文は、保育者・初等教員養成課程学生を対象に、「子どもの学びの相似形」の視点から、「遊びの再経験」及び「遊びの再構成」の二つの活動を中心とするわらべうたの遊び直し経験を軸とした授業構成を考案し、その有効性について実践研究を通して明らかにしたものである。その結果、以下の2点が明らかになった。①本研究において考案した授業構成により、子どもの立場に立って遊びを経験することで、単に「楽しかった」で終わることなく、楽しさの要因となっているわらべうたの特徴や教育的意義などについて実感的に気付くことができたこと。②その経験を保育者役として実施する〔模擬実践〕における指導につなげ、保育者の立場から子どもとの関係を想察する視点を実践的に身に付けることができたこと。 本研究は、保育者養成の音楽授業において、教師の実践的指導力の素地を養うために授業の質的転換を図ろうとする新たな授業構成の提案であり、そこには高い独創性が認められ、学校音楽教育実践学に大きく貢献するものであると評価される。 | |
| 審査委員会 (◯印は審査委員長) |
理事以外(外部委員) | 石田一志(音楽評論家) |
| 松尾葉子(指揮者) | ||
| 〇松本絵美子(国立音楽大学附属小学校) | ||
| 常任理事(内部委員) | 小川由美(琉球大学教育学部教授) | |
| 鉄口真理子(鳴門教育大学教授) | ||
| 清水 匠(つくば市立松代小学校) |
日本学校音楽教育実践学会
〒772-8502
徳島県鳴門市鳴門町高島中島748
鳴門教育大学大学院 学校教育研究科
鉄口研究室気付
日本学校音楽教育実践学会事務局
TEL &FAX 088-687-6467
E-mail ongakujissen@yahoo.co.jp